
介護現場では日々さまざまな出来事が発生しますが、時にはヒヤリとする場面や、思わぬ事故につながりかねない状況に直面することもあるでしょう。
こうした危険を未然に防ぐために重要なのが「ヒヤリハット」の考え方です。
本記事では介護現場におけるヒヤリハットについて、事例集を交えながら分かりやすく解説していきます。
事故を防ぐための意識を高め、より安全な介護環境をつくるためにぜひ参考にしてください。
ヒヤリハットとは?
ヒヤリハットとは、事故やケガには至らなかったものの、後一歩で重大な事故などのトラブルになりかねない出来事を指します。
「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりする場面が由来で、これを適切に記録・分析し、対策を講じることで重大事故の発生を防ぐことが目的です。
施設によってヒヤリハットの書式や対策に関する考え方はさまざまですが、ヒヤリハットを多く出すことによって、事故報告が減るといった例もあります。
アメリカの損害保険会社の安全技師であったハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが提唱した「ハインリッヒの法則」によると、1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故、そして300件のヒヤリとするシーンが存在するとされています。
この法則からも分かるように、ヒヤリハットの段階で適切な対策を講じることが、事故防止の重要なカギです。
介護現場のヒヤリハット事例集
ここでは、実際の介護現場でもっとも起こりやすいヒヤリハットの事例を、原因や対策も交えて解説していきます。
下記で紹介する事例を知っておくことで、実際の介護現場で働く際に事故を未然に防ぐ考え方や意識が芽生えるでしょう。
ヒヤリハット事例①『転倒・転落』
| 概要 | リビングの自席で過ごされていたが、利用者が立ち上がり、自分の居室に向かう途中の廊下でつまずき転びそうになる。 |
| 対応 | 介護職員が居室まで付き添う。 |
| 原因 | 靴をしっかり履けていなかった(靴のかかと部分を踏んだ状態だった)。 基本的に自分で歩けるが、疲れてしまうとふらつくことがある。 |
| 対策 | 利用者がしっかり靴を履けているか、小まめに確認する。リビングから居室への動線に、ソファーなど利用者が休憩できるスペースを設置する。 |
| 概要 | リビングにて車椅子で過ごされていたが、利用者の体動によりバランスを崩し、ずり落ちそうになる。 |
| 対応 | 介護職員が座り直しの介助を行う。 |
| 原因 | 姿勢を整えるため自分で座り直そうと動いた、もしくは長い時間車椅子で過ごしていたため疲れにより姿勢が崩れたか。 |
| 対策 | 利用者の姿勢に注意し、崩れが見られた際は座り直しの介助を行う。座位保持のクッションが適切かどうか確認し、場合によっては変更する。車椅子で過ごす際のシーティングを検討する。 |
ヒヤリハット事例②『食事』
| 概要 | 朝の食事に普段よりも時間がかかっている様子があるため、利用者の口腔内を確認すると入れ歯をしていない状態だった。 |
| 対応 | すぐにうがいをしてもらい口腔内の食物を除去し、居室にあった入れ歯を装着してもらう。 |
| 原因 | ほぼ自立している方であり、利用者自身に入れ歯の管理をしてもらっていたため、職員が義歯の装着に関して意識が欠けていた。 利用者の認知機能が低下している可能性がある。 |
| 対策 | 朝に利用者がリビングに来られた際は、入れ歯が入っているか口腔内を確認する。 入れ歯の管理について、職員間で情報共有し改善案を検討する。 |
ヤリハット事例③『嚥下』
| 概要 | 食事中に利用者がお茶を飲んだ後にむせはじめ、しばらく咳き込みが続いた。 |
| 対応 | 介護職員が声をかけたり、落ち着くまで背中をさすったりした。 |
| 原因 | トロミなしの水分を提供していたが、嚥下機能が衰えている可能性がある。 もともと食事のペースが早く一気に飲もうとする傾向がある。 |
| 対策 | 水分にトロミ剤を入れて飲み込みの様子を確認し、適切な量を検討していく。 食事を提供する際は、本人にゆっくり食事や水分をとるように声をかける。 |
ヒヤリハット事例④『服薬』
| 概要 | 朝食後に夜勤明けの介護職員が利用者の服薬介助のため薬を持っていくが、直前でほかの人の薬であることに気づいた。 |
| 対応 | 利用者に謝罪し、すぐに本人用の薬を持ち、名前を確認し服薬してもらう。 |
| 原因 | 職員が夜勤明けだったため、疲労により判断能力が低下していた。 普段、手慣れた介助であり、意識が欠けていた。 |
| 対策 | 服薬の介助は夜勤明けの職員ではなく早番の職員が行うなどのルール作りをする。 服薬介助に入る前に、名前をしっかり確認し他職員にも見せるなど、ダブルチェックを行う。 |
ヒヤリハット事例⑤『更衣』
| 概要 | 居室にて利用者のパジャマへの更衣の見守りをしていたが、立った状態で着替えをしており、ズボンを履く際にバランスを崩して転びそうになる。 |
| 対応 | 介護職員がそばにいたため転ぶ前に体を支え、ベッドに座りながら着替えるように声をかける。 |
| 原因 | 利用者の昔からの習慣により、立った状態で着替えを行っていたが、ADLが低下している可能性がある。 夜だったため、一日の疲れによりふらついてしまったか。 |
| 対策 | 更衣の際は、ベッドや椅子などを使って座りながら行うように声をかける。 疲れが出る可能性を考慮し、更衣や就寝時の時間帯を再検討していく。 |
ヒヤリハット事例⑥『入浴』
| 概要 | 入浴中に浴槽内で利用者の体が浮き、バランスが崩れて顔がお湯の中に入りそうになってしまった。 |
| 対応 | 介護職員が利用者の両脇を持ち体を支える。 |
| 原因 | 利用者の体重が軽く、体が浮いてしまった。 介護職員が利用者の体型による、入浴時のリスクについて把握していなかった。 |
| 対策 | 利用者の体型に合うようにお湯の量を調節する。 場合によっては職員2人対応で入浴介助を行ったり、浴槽内に体を支えるマットやベルトなど適切な福祉用具を取り入れたりと、リスク対策を検討する。 |
ヒヤリハット事例⑦『移動・移乗』
| 概要 | 廊下にて車椅子で移動中に、利用者が怖がって体を動かし転落しそうになる。 |
| 対応 | すぐに車椅子を止めて利用者の体を支え、安心するよう声かけした。 |
| 原因 | もともと介助に対する恐怖心が強く、移動時にも何かにつかまろうとして手を前に出す動きが見られる。 介護職員の車椅子を押すスピードが、本人にとっては速く感じたか。 |
| 対策 | 本人の恐怖心が強いことを考慮し、移動時も安心するような声かけを行ったり、気を紛らわせる話題をふったりする。 車椅子を押すスピードを考慮し、本人に確認しながら移動介助を行う。 |
| 概要 | 居室にて、車椅子からベッドへの移乗介助の際にベッドでの座りが浅く、利用者の体がずり落ちそうになる。 |
| 対応 | 介護職員が利用者の体を支え直し、ベッドに横になってもらう。 |
| 原因 | 利用者の体重が重く、うまく体を支えることができなかった。 ベッドの高さが上がっている状態のまま移乗してしまい、バランスが崩れた。 |
| 対策 | 移乗時はスライドボードを使用するなど、福祉用具を検討する。 移乗時は車椅子とベッドの高さが合っているか、安全に移乗できるか確認する。 |
介護現場のヒヤリハット報告書の書き方と活用方法
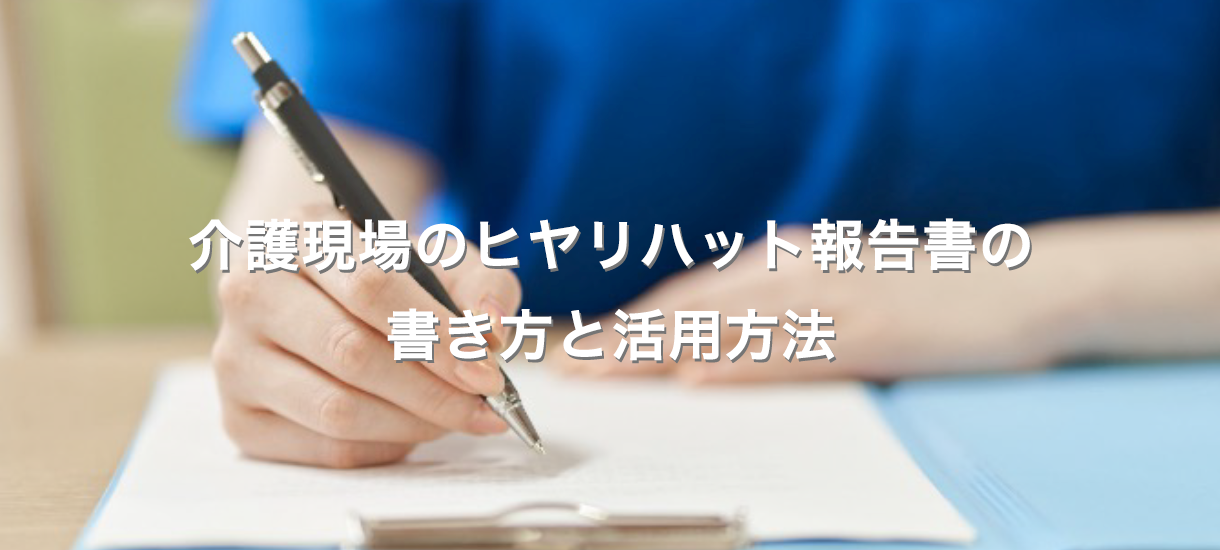
ここでは、ヒヤリハット報告書の書き方や注意点、活用方法について解説をしていきます。
これらのポイントを押さえることによって、誰が見ても分かりやすいヒヤリハット報告書が作成できるようになるので、ぜひ参考にしてください。
ヒヤリハット報告書の書き方と注意点
ヒヤリハット報告書を書く際は、下記2点を意識することが大切です。
- 5W1Hを意識して書く
- 客観的な事実を書く
スムーズに作成するためにも、確認していきましょう。
5W1Hを意識して書く
5W1Hとは下記を指します。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| When(いつ) | 〇月〇日 〇時〇分 |
| Where(どこで) | リビングの自席で過ごされていたが、 |
| Who(誰が) | 利用者が立ち上がり、 |
| What(何を) | 自分の居室に向かう途中の廊下でつまずき転びそうになる。 |
| Why(どうして) | 靴をしっかり履けていなかった。 基本的に自分で歩けるが、疲れてしまうとふらつくことがある。 |
| How(今後どのようにしていく) | 利用者がしっかり靴を履けているか、小まめに確認する。 リビングから居室への動線に、ソファーなど利用者が休憩できるスペースを設置する。 |
これらを意識して具体的に記載することが重要です。
客観的な事実を書く
ヒヤリハット報告は、主観的な想像や感想を交えるのではなく、客観的な事実を明確に記載することが求められます。
例えば「~だろう」や「~だと思う」といった報告書になってしまうと、事実と想像が入り交り、ほかの介護職員が見たときに混乱を生じさせてしまいます。
また、職員の個人的な目線や責任逃れのように思われる可能性もあり、事実に基づいた適切な対策がとれなくなるおそれもあるでしょう。
客観的な事実を書くことで、その場にいなかった介護職員や他職種にも分かりやすい内容になり、印象もよくなります。
ヒヤリハットの活用
介護職員の中には、ヒヤリハットを出すことに自身のミスや不注意といったマイナスなイメージを持ち、作成をためらう人もいます。
しかし、ヒヤリハットは介護現場での事故を防止するリスクマネジメントを実施していく上で、重要な要素です。
ここでは、ヒヤリハットがどのように活用されていくかを見ていきましょう。
情報の共有
ヒヤリハットの情報をほかの介護職員や他職種と共有することで、その利用者に関わるすべての人が、ヒヤリハットで起きたリスクに対する意識を高めます。
これにより、違う介護職員が対応した際にも、安全なケアを行うことが可能となります。
また、ヒヤリハットについて話し合うことで、介護職員同士や他職種との信頼関係がさらに深まり、チームケアの質が上がる点もメリットです。
事故の防止
ヒヤリハットの段階で原因や対策について検討すると、その先にある事故を未然に防ぐことにつながります。
例えば、車椅子から体がずり落ちそうになっている例を放置すると、その後実際に転落してしまうことも十分に考えられます。
転落をしてしまうとケガをする可能性はもちろん、場合によっては骨折という重大事故につながるおそれもあるでしょう。
ヒヤリハットを出すことは、むしろ事故防止への意識強化であり、結果的には事故の減少につながります。
対応の証明
ヒヤリハットの記録は、施設や企業にとって重要な証拠となります。
万が一事故が発生した場合でも、事前にリスク対策を講じていたことを示す資料として活用できるでしょう。
例えば、介護施設で転倒事故が発生した場合、「以前から類似のヒヤリハットが報告され、それに基づいた対策を行っていた」という記録があれば、施設側の適切な対応を証明する材料となります。
これは、法的なトラブルに対応するだけでなく、利用者の家族からの信頼を得るためにも有効です。
ヒヤリハットを軽視するリスク
前述のとおり、ヒヤリハットをマイナスなものと捉えて隠したり、大したことではないと捉えて軽視したりすると、重大事故につながるリスクが高まります。 些細なことでもリスクを感じた場合は、ヒヤリハットの記録を怠らずに、ほかの介護職員や他職種と連携し、改善案を検討していくことが大切です。
介護現場に絆Coreシリーズを導入しよう!
介護現場では日々多くの記録作業が発生します。
ヒヤリハット報告書もその一つであり、記入漏れや情報の共有遅れが発生しやすく、スタッフの負担となることも少なくありません。
そこで役立つのが、クラウド対応の介護システム「絆Coreシリーズ」です。ここでは、介護システム「絆Coreシリーズ」について紹介していきます。
スタッフの業務効率化を支援
絆Coreシリーズを導入することで、介護記録をデジタル化し、業務の効率化を実現できます。
タブレットなどを使用して、記録をリアルタイムで入力できるため、業務の正確性が向上し、スタッフ間の情報共有もスムーズになります。
さらに、入力されたデータは自動的にデータの取り込みが行われるため、紙の記録のように紛失の心配がありません。
リスクマネジメントも可能
絆Coreシリーズにはヒヤリハットの報告・管理機能が搭載されており、すぐに記録・共有することができます。これにより、施設内で発生したヒヤリハットをデータベース化し、類似した事例の再発防止に役立てることが可能です。また、過去の事例が分析しやすくなることで、施設全体のリスクマネジメントの質を向上させられるでしょう。
まとめ

ヒヤリハットとは、事故やケガには至らなかったものの、一歩間違えれば重大な事故につながりかねない出来事を指します。
介護現場では利用者の安全を確保するために、こうした事例を記録し、未然に防ぐ取り組みが重要です。実際のヒヤリハット事例を知ることで、介護現場で働く際に事故を未然に防ぐ意識が高まります。また、ヒヤリハットを記録する際は、絆Coreシリーズの導入がおすすめです。
データを生かしたリスク管理を徹底し、より安心・安全な介護現場を目指しましょう。





