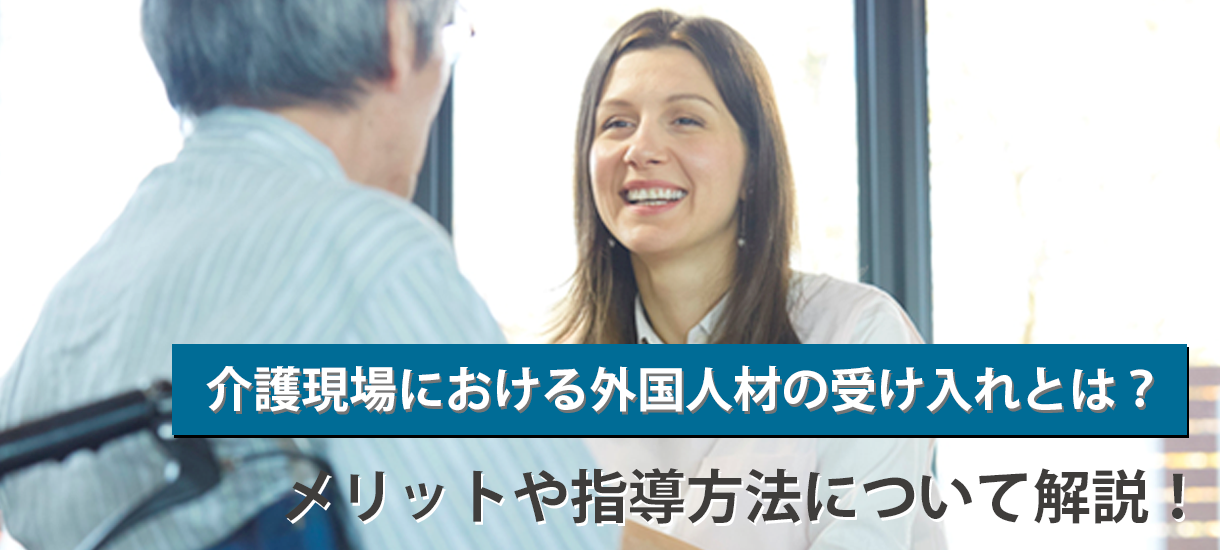
介護業界では、高齢化に伴う介護需要の増加に対する人材不足が深刻な課題ですが、その解決策の一つとして外国人材の受け入れが注目されています。多様な文化や価値観を取り入れることで、介護現場の労働力を確保できます。本記事では、介護職で外国人材を受け入れられる制度と、注意点について詳しく解説していきます。
最後まで読んで、外国人材をスムーズに受け入れましょう。
介護で外国人材を受け入れるための4つの制度

外国人が日本で働くために必要な資格として「在留資格」があります。さらに、外国人材を介護職として受け入れるための仕組みとして、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能1号という4つの制度が存在します。
それぞれ一つずつ解説していくため、確認していきましょう。
EPA(経済連携協定):国家資格取得が必要
EPAとは、特定の国や地域同士での貿易や投資を促進する条約のことです。
日本ではインドネシア・フィリピン・ベトナムとの各協定に基づき、外国人介護福祉士候補者の受け入れを行っています。
日本の場合、介護や看護に関する知識を持った人材が日本語研修を受けて日本に入国し、受け入れ施設で働きながら国家試験の合格を目指します。
入国4年目に介護福祉士の国家試験に合格すれば在留期間を更新しながら永続的に働くことができますが、不合格の場合は帰国しなければいけません。
受け入れ施設には、外国人材が介護福祉士の国家試験に合格し、その後も介護職として日本に滞在してもらうように、国家試験対策や日本語学習などの研修実施が義務付けられています。
なお、受け入れたい場合は国際厚生事業団(JICWELS)によるマッチングが必要です。
在留資格「介護」:長期間滞在が可能
専門的・技術的分野への外国人労働者の受け入れを目的とした制度です。
日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業後に介護福祉士を取得すると、「介護」という在留資格を取得できます。
取得後は在留資格に制限されずに日本での長期滞在が可能になり、家族と住むこともできるようになります。
令和2年4月1日以降は実務経験を経て介護福祉士を取得した人も、在留資格「介護」への移行対象となりました。
技能実習:人材を確保しやすい
技能実習とは、国際貢献のために、発展途上国などの外国人を日本で最長5年間受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
実習生は入国後、日本語と介護の基礎に関する講習を受けた後に、介護事業所で受け入れられます。
入国1年後と3年後に受ける試験に合格することで、それぞれ追加で2年間実習を受けられるようになるため、人材が確保しやすくなる点がメリットです。
5年間の実習後は帰国して、母国で介護業務に従事します。
なお、技能実習期間中に介護福祉士を取得すれば、在留資格「介護」への変更が可能になり、日本で働くこともできます。
ただし、技能実習制度は2030年までに廃止され、代わりに「育成就労制度」が2027年からスタートする予定です。
育成就労制度は、在留期間や受け入れ時の条件などが技能実習制度と異なるため、移行時期に技能実習生を受け入れたい場合は注意する必要があります。
特定技能1号:幅広い業務に従事できる
特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れる制度です。
介護のほかにも建設や自動車整備、外食業などが対象で、国内人材の確保が難しい分野での労働力補充を目的としています。
特定技能1号として介護分野で働く外国人は、技能水準と日本語能力水準の試験に合格した上で入国します。
5年後には原則として帰国することになりますが、介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格を「介護」に変更し、長期的に日本で働くことも可能です。
介護職で外国人材を受け入れるメリットと課題
続いては、介護現場で外国人材を受け入れた場合の、メリットや課題について解説していきます。
実際に外国人材の方と働く際に考慮しておくべきことや、注意するポイントについて学べるでしょう。
外国人材を受け入れるメリット
介護現場において外国人材を受け入れることで「人手不足の解消」および「国際貢献」につながる点がメリットです。
特に介護現場における人手不足の解消は、高齢化が進む日本にとって、この上ない助けとなります。
人手不足の解消
日本の介護業界は、慢性的な人手不足に直面しています。
よって、外国人材の活用で施設の運営を安定させることはもちろん、若い労働力を獲得しやすくなり、体力が必要な介護業務での活躍も期待できるでしょう。
また、日本人の応募が集まりにくい地方の施設でも、条件次第で採用が可能となり、地域の人手不足解消にも貢献する可能性があります。
国際貢献
介護現場で外国人材を受け入れることは、日本の介護技術を学んだ外国人が、将来的に自国の介護分野の発展に貢献する機会を生み出します。
日本の技術やノウハウが広まることで、世界的な介護水準の向上につながるでしょう。
また、外国人材が日本で得た知識や経験を自国に還元することで、介護施設の運営改善や新たなケア技術の導入が期待されます。
さらに、介護を通じた文化交流が相互理解を深め、国際的な協力や信頼関係の構築にも役立つでしょう。
外国人材を受け入れる課題
介護現場にとって外国人材の雇用は、人手不足の解消につながる一方で、いくつかの課題もあります。
下記で詳しく解説していきます。
コミュニケーションが難しい可能性がある
言葉の壁によって、利用者や介護員との円滑なコミュニケーションが難しくなることがあります。
そのため、日本語教育や簡単な言葉で説明する工夫が求められます。
また、イラストなどを用いたボードを作成してコミュニケーションの補助を行ったり、多言語対応の翻訳アプリを活用したりすることも、視野に入れるとよいでしょう。
日本の文化や習慣に関する研修を実施し、相互理解を深めるのも方法の一つです。
在留資格の手続きが必要になる
外国人材を受け入れる際は、在留資格の手続きや管理が必要であり、介護事業者の負担となる場合があります。在留資格の取得や更新、就労条件の管理など、外国人の介護職員を雇用するための法的手続きは多岐にわたります。
これらの手続きを適切に行わなければ、外国人介護士が就労を継続できなくなるため、行政書士や社会保険労務士などの専門家のサポートを受けたり、在留資格や就労条件を一元管理できる専用のシステムを導入したりする必要があるでしょう。
また、施設内で在留資格管理の担当者を育成するのも一つの手段です。
介護現場での外国人材の指導方法
続いては、外国人材の指導をする際のポイントについて解説していきます。
ポイントを押さえておくことで、円滑なコミュニケーションにつながり、双方が気持ちよく仕事ができるようになるでしょう。
ゆっくりと分かりやすく話す
外国人に日本語を理解してもらうために、ゆっくりと分かりやすい日本語で話すことを心がけましょう。介護現場では時間に余裕がなく、早口になったり、専門用語が出てしまったりするケースもあります。中には、間違った認識のまま仕事をしてしまう外国人もおり、重大なミスが生じることも少なくありません。話す内容は短い文章にまとめて、相手が理解しているかどうかを適宜確認し、場合によっては複唱してもらうことも必要です。
質問しやすい雰囲気を作る
仕事をする上で「報告・連絡・相談」は重要な考え方です。
外国人が何かを話そうとしているときは、じっくり耳を傾けてあげることが大事です。
指導する職員に余裕がなく、イライラしてしまうと、外国人に恐怖を与えます。
指導に対して分かっているふりをして働いてしまうケースも、珍しくありません。
質問や相談、雑談などが気軽にできる職場は、良好な人間関係を築きやすいでしょう。
キャリアパスを明示する
昇格や昇給制度、段階ごとの評価など、キャリアパスをあらかじめ明示しておくことも、外国人材の安心やモチベーションにつながります。
モチベーションを維持することで、将来的に長く働いてもらえる可能性が高くなります。
今後の目標や現状の達成度などを定期的にフィードバックし、モチベーションを上げる指導を行うとよいでしょう。
介護職で外国人材を受け入れた施設の声
最後に、実際に外国人材を受け入れた介護施設の声を紹介していきます。
施設の声①
「働き始めたばかりの頃は、外国人スタッフの仕事に対する考え方に疑問を抱いたこともあります。
しかし、日本の仕事に対する考え方を説明することで、今では熱心に仕事をしてくれています。
また、外国人スタッフが入ってくれたおかげで人手不足が解消され、利用者の皆さんへの対応に余裕ができました。」
施設の声➁
「最初は言葉の壁がありましたが、研修を通じて意思疎通がスムーズになり、今では楽しく仕事ができています。
言葉の壁をクリアすることで、異文化交流ができるのも魅力です。
また、外国人の丁寧な日本語により利用者に方も安心して過ごしている様子があり、私たちも見習うべきことがあると感じさせられます。」
まとめ

介護業界で外国人材を受け入れる制度には、EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能1号の4つがあります。
外国人材の受け入れには、人手不足の解消や国際貢献といったメリットがある一方で、言語の壁や手続きの負担といった課題も存在します。
そのため、受け入れ体制を整えることが大切です。
実際の施設でも、最初は文化や言葉の違いに戸惑うものの、研修や指導を通じて職員と良好な関係を築いている事例が増えています。
適切なサポートを行い、外国人材と共に成長できる介護施設を目指しましょう。



